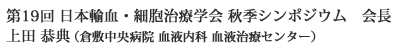

第19回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウムは、11月16日(金)岡山コンベンションセンター(ママカリフォーラム)で開催されます。
前日午前中には川崎医科大学(和田秀穂教授)を当番校に平成24年度全国大学病院輸血部会議、午後には輸血・細胞治療学会の各種委員会が開催されます。
倉敷中央病院の輸血部門は1980年に、浮田昌彦先生、矢切良穂先生によって、輸血センタ―として開設され、その後ヘムアフェレ-シス等の治療にも深くかかわるため、血液治療センターと改称いたしました。
現在では、多職種によるセンターとして、医師(血液内科兼務)、臨床検査技師、管理薬剤師、アフェレ-シスナース、造血細胞移植コーディネーターが、臨床検査科、薬剤部や臨床工学技士の協力を得て、輸血関連業務のほか、遠心、膜、吸着剤、不織布等を用いたヘムアフェレシス全般、濃縮腹水再静注の腹水処理、造血幹細胞移植や再生医療に向けての細胞採取、処理、保存、造血細胞移植ドナーコーディネート等の業務に取り組んでおります。
今回のシンポジウムのテーマを『エビデンスを創る』とさせていただきました。輸血医療は、多くの場合非常に危機的な状況で行われるため、エビデンスが作りづらい領域です。またエビデンスですら更新されてゆくことはしばしば経験することです。エビデンスを客観的に眺めつつ、必要に応じて医療に生かすことは非常に重要ですが、その一方で、その時代の限界の中でエビデンスを創る努力をすることは、我々の務めであろうと思われます。今回の特別講演にはカナダから、Gail Rock先生をお招きしました。TTPの論文には必ず引用されるCanadian apheresis study groupによる後天性TTPの治療での血漿交換とFFP輸注のランダム化比較試験で血漿交換の優位性を示された先生であり、この論文は後にADAMTS13とその抗体が発見され、彼女たちの導いた結果の意味付けがなされるという、TTPにとってもアフェレ-シスにとっても、大きな意味を持つ報告となりました。
その他の輸血の領域においても大きな業績を残されています。今回は TTP:Plasma Exchange and Other Treatment Modalities.というTitleでTTPの治療に長年取り組んでこられた真髄をお聞かせいただけるものと思います。
シンポジウム1では、輸血、移植の基礎になり、現在も新しい知見が積み重ねられている組織適合性の現状が、第一線で活躍する研究者によって議論されます。シンポジウム2では、輸血医療という行政や公衆衛生と密接なかかわりを持つ領域で、なかなか踏み込んだ議論が行いにくい、『赤十字血液センターの製造業務の集約化』、『自己血輸血』、『輸血管理料』についてあえて取組み、各分野に精通した方々を演者と司会者にお迎えし、Pros and Consの手法を用いて論点を明らかにしたいと考えました。フロアからも積極的に議論に参加していただきたいと思います。今回は、シンポジウム終了後にサテライトセミナーとして輸血認定技師更新講座を設けております。学会員でない参加者もセミナーのみ無料でご参加いただけますのでふるってご参加ください。
会場は岡山駅と連続しており、サテライトセミナー終了後でも、東京、鹿児島までお帰りになることが可能な時間設定といたしました。 JRに乗れば17分で倉敷に到着です。もちろんさらにご一泊いただければ、瀬戸内はもとより、山陰、四国まで足を延ばすことも十分可能です。
是非、秋の岡山で、ご一緒にエビデンスを創ろうではありませんか。